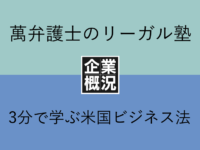M&A(合併買収) ~好調なりの悩み?~
企業概況 発行日:
Jweekly 発行日:
今年最後の本寄稿は、「判例で学ぶ米国法」シリーズの第50回目の記事とあって、景気の良いトピックについてお話しよう。2014年度は、米国M&A市場が2008年のリーマンショック以降初めて最高取引額を記録した年であったが、本年度は、11月の時点で既に総取引額が4兆ドルを超え、去年を30%以上上回ることが予想されている。 (Thomson Reuters, MA Q3 2015調べ)
テクノロジー分野ではDell がEMC Corporationを業界最高値で買収(670億ドル)、医薬品分野では、AbbVie によるPharmacyclics の買収(210億ドル)や、PfizerによるAllerganの買収(1千600億ドル)などの大規模なM&A取引が報告されている。
これらの活発な動きに政府が目を光らせているのは、独占禁止法違反とコーポレート・インバージョンによる税の取り逃がしである。
<米独占禁止法>
米国における独占禁止法は、消費者保護を目的として、公正な競争を推進するために設けられた連邦及び州の一連の法律を指し、通商の抑制、独占行為、価格差別(同一品/サービスを顧客によって別価格で販売すること)や抱き合わせ販売、公正な市場競争を妨げる企業買収等を禁止している。1911年の最高裁判決として、ジョン D.ロックフェラー氏が所有していたスタンダードオイルカンパニーが独禁法違反で30社以上の会社に分割させられた事件(Standard Oil Co. of New Jersey v. United States)は有名だ。又、1999年、連邦裁判所の第一審でマイクロソフト社が分割を命じられたが、控訴審ではその判決が覆され和解が成立したのも記憶に新しい。今年の12月7日、連邦取引委員会(FTC)は、Staples, Inc.によるOffice Depot, Inc. の買収計画(63億ドル)が独禁法に違反するとして、連邦裁判所に差し止め命令を求めて訴え結果が待たれる。
現在では取引額が7, 630万ドルを超えるM&Aの場合、連邦取引委員会又は法務省の許可を得なければならなず、違法と判断される場合は取引の中止や見直しが要請される。
<コーポレート・インバージョン>
最近の国際企業間のM&Aには、コーポレート・インバージョンと呼ばれる形態が見られる。コーポレート・インバージョンとは、企業合併により税負担の高い本国から低い外国に企業の籍を移すものの会社の主要機能は本国に残すという、節税対策を意味する。オバマ大統領は、節税目的でコーポレート・インバージョンを行う企業を「非愛国的」だと公然と非難し、盛り上がる米大統領選のディベートでもその是非が議論されている。
先進国のうち法人税率が低い国々には、アイルランド‐12.5%、英国‐20%、カナダ‐26.5%(連邦税:15%、地方税-オンタリオ:11.5%)などが挙げられる。それと比較し米国の連邦法人税は、所得額に応じた15%~35%の累進課税となっており、州税も含めると40%を超える場合があるのが現状だ(ちなみに日本は33.06%)。更に米国籍の企業が、海外に子会社を持つ場合、その子会社の事業収入も課税対象とされる場合がある。従って、世界中に子会社を持つ米国企業は、米国外を源泉とする事業収入に対してまでも最高35%の課税を受ける可能性がある。
これに対しアイルランドや英国、カナダは、国内を源泉とする事業収入に対してのみ課税し、海外の子会社の事業収入は課税対象にならない。世界中に子会社を持つ米国法人が、法人税率の低い国に移籍した場合、その節税額はかなりの金額にのぼることが予想される。過去10年間で47件にも及ぶ節税対策のインバージョンが報告されている(国会調査サービス、調べ)。
今年11月23日、Pfizer社は、シワ取り効果があるといわれている薬品「ボトックス」の製造元であるAllergan社を1千600億ドルで買収する旨を発表した。合併後のPfizer社は、アイルランドに籍を置き、米国法人はその子会社となる予定である。このM&Aディールが完結すれば、米国政府は、米国を源泉とする米国子会社の事業収入に対してのみ課税でき、海外を源泉とする同社の事業収入を取り逃がすことになってしまう。昨年9月、オバマ政権は、節税目的のコーポレート・インバージョンを制限する規制を設けたが、期待したほどの効果が見られていないのが現状だ。一部の批評家によると、コーポレート・インバージョンが問題なのではなく、米国の税制度が問題であり、抜本的な税改正が必要だと指摘している。
本記事の内容は、一般的事実を述べているだけであり、特定の状況に対する法的アドバイスではなく、それを意図したものでもない。個々の状況に対しての法的アドバイスは、直接当事務所にご連絡頂くか、専門の弁護士にご相談されることをお勧めする。
J weekly https://jweeklyusa.com/