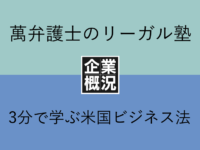企業の不正を正す手段 ~集団訴訟の行方~
企業概況 発行日:
Jweekly 発行日:
読者の皆さんは、もし大企業の不正行為により少額の犠牲を強いられた場合、その企業を法廷に訴えるであろうか?訴訟には莫大な費用と時間、労力がかかるため、たとえ勝ち目があったとしても損害賠償金が少額となれば、資産家であっても訴訟を提起する人はいないだろう。そこで、毛利元成の「三矢の訓」と同様、同じような状況に置かれた多数の原告が束になり「集団訴訟」という形式で訴える方法がある。集団訴訟は、法執行機関の及ばないところで、消費者が企業の不正を追及できる重要な機能を果たしている。今回は、この集団訴訟の経緯と今後の行方を探ってみよう。
<経緯>
英国においては、既に中世の時代から同様な状況に置かれた多数の農民を代表した数人が法廷で訴訟を行う慣習があった。この慣習が、植民地時代の米国においても受け継がれ、19世紀に法的手続きとして確立され、1966年の連邦民事訴訟規則の大幅改正をきっかけに、集団訴訟が訴訟手段として市民権を得た。20世紀後半、消費者運動や環境保護運動が高まる中、自動車会社や石油会社を相手取った集団訴訟は、茶の間のニュースをにぎわすことになった。中でも消費者を代表し全米の各州政府がタバコ会社6社を相手取って提訴した訴訟では、1998年、25年目にしてようやく和解に至ったものの、和解金の総額が2千60億ドルにも上ったのは有名である。
一方、企業としては、莫大な訴訟費用や損害賠償義務のリスクが伴う集団訴訟を極力避けたいのが本音である。立て続く集団訴訟に悩まされた企業側のロビー活動の結果、2005年2月ブッシュ政権下の米議会は、Class Action Fairness Act of 2005(2005年集団訴訟公正法)を可決し、損害賠償請求額が5百万ドルを超える訴訟の管轄を原告に有利と見られる州裁判所から連邦裁判所へ移すことを容易にした。更に2005年9月3日に他界したウィリアム・レンクウィスト最高裁長官の後任として、ブッシュ大統領に指名されたジョン・ロバーツ長官を始めとする現在の保守派判事達は、第二次世界大戦以来、個人の利益より企業利益を優先する傾向にあると一部で指摘されている(ミネソタ・ロー・レビュー調べ)。
<集団訴訟の要件>
「集団訴訟」という形式で訴訟を提起する場合は、連邦民事訴訟規則23条に基づき、以下の4つの要件を満たしていることが必要である(①多数:集団が多数存在する、②共通性:集団に共通する法律上又は事実上の問題点が存在する、③典型性:代表当事者の請求又は抗弁が、その集団の典型例である、④適正性:代表当事者が集団の利権を公正かつ適切に保護する)。しかし、過去数年の最高裁の判例において、集団訴訟の要件の審査が厳しくなったのは事実である。
<集団訴訟が却下された最近の判例>
2011年6月に米最高裁で可決された、ウォルマート対デューク裁判では、150万人もの女性従業員が、売上総額で世界最大の企業ウォルマートを相手取り、女性に対する不平等な賃金及び昇格機会の否定などの同社の行為が公民権法第7章に違反するとして、損害賠償を求めていた。しかし、米最高裁は集団訴訟を提起するための要件の一つ「共通性」に欠けるとして、訴えを退けた。
更に2013年3月、米最高裁はコムキャスト対ベアレンド裁判において、米国最大のケーブルTV会社を相手取った200万人の消費者による集団訴訟を5対4の判決で却下した。フィラデルフィア地区のケーブルTV加入者は、コムキャストが市場の独占を図るため選定した特定地区にある他のケーブル会社を買収し不当に料金を釣り上げた行為は、独占禁止法に違反するとして集団訴訟を提起しようとした。しかし、最高裁は、原告らが被った被害は「共通性」に欠けるとして集団訴訟を認めなかった。莫大な損害賠償金の支払いを免れたウォルマートやコムキャストのみならず、米コーポレート業界がこれらの最高裁判決を全面的に支持したのは言うまでもない。しかし、今年の1月、この流れを変えるような最高裁判決が下された。
<キャンベル‐エワルド社 対 ゴメズ (2016年1月)>
広告会社であるキャンベル社は、米海軍のために応募者を募るテキストメッセージを18~24歳の若者で、かつ、海軍からの広告を受けることを承諾している者に対して送っていた。メッセージを受けた10万人以上の受信者のうち、ゴメズ氏は、年齢40歳であり広告の受信を許可していないとして、キャンベル社に対し、無許可の宣伝広告の送信を禁止する電話消費者保護法に違反したとして集団訴訟を起こした。これに対し、キャンベル社は、ゴメズ氏他が集団訴訟を提起する以前に、同氏が当初の訴状で示した損害賠償等の要求を全て満たした和解案をゴメズ氏に提示してあると主張した。更に、同氏が受け入れを拒否したものの、同和解案を提示した時点で訴因は消滅したとして、集団訴訟は無効であると反論した。これに対し、最高裁は、ゴメズ氏が当該和解案を拒否したため和解は成立しておらず、訴因は未だ存在しているとして集団訴訟の訴えを認めた。
<考察>
もし、最高裁が、被告側の和解案の提示により訴因が消滅したと判示していた場合、今後、企業は集団訴訟を回避するために、例え代表当事者が受け入れなくても和解案を提示すればよいことになる。今回の最高裁判決により、集団訴訟を提訴する原告側の利権が保護された結果となった。今年2月のスカリア判事の逝去により保守派とリベラル派のバランスが崩れる中、今後の最高裁の方向性に注目したい。
本記事の内容は、一般的事実を述べているだけであり、特定の状況に対する法的アドバイスではなく、それを意図したものでもない。個々の状況に対しての法的アドバイスは、直接当事務所にご連絡頂くか、専門の弁護士にご相談されることをお勧めする。
J weekly https://jweeklyusa.com/