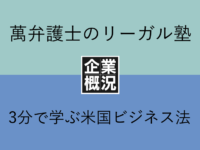~公民権法第七編と報復的行為~
企業概況 発行日:
Jweekly 発行日:
1964年の米国公民権法第七編(通称:タイトル・セブン)は、「人種、肌の色、宗教、性別、出身国」を理由とする雇用上の差別を禁止するとともに、雇用主による差別的行為に反対したり告発や調査等を支援する従業員に対する報復的行為も禁止している。
このタイトル・セブンによって設立された雇用機会均等委員会(EEOC)は、同法に基づく差別を調査し、取り締まりを行う機関である。EEOC発表の統計調査によると、2012年にEEOCに申し立てられた差別に関する告発総数は約99万4千件で、そのうち報復的行為に関する告発は、前年の37.4%から増え38.1%にものぼっており、過去15年間で2倍に増えている。「差別に関して苦情を提出したりEEOCに告発した、或いは関連の調査に協力した」ことを理由に仕事の上で不利な扱いを受けたとの訴えは非常に多いのだ。一方では、差別被害者のうち実に62%が何も申立を行なわない(沈黙している)と言われるが、しばしば発生する報復的行為を恐れる心理が、こういった高い沈黙率に貢献していることは間違いない。
しかし、雇用主が行う降格や減給、解雇といった雇用上の判断が、実際に報復的行為と看做されるには、どこまでの因果関係が必要なのかという解釈は微妙で、法廷の判決が二転三転することも珍しくない。今年の6月24日に最高裁が出したUniversity of Texas Southwestern Medical Center v Nassar(テキサス南西メディカルセンター大学対ナサール)の判決も、下級裁判所の審理結果を覆す内容となった。
<背景>
テキサス南西メディカルセンター大学(以降「大学」と呼ぶ)は、医科大学であり、パークランド記念病院(ダラスの大病院で、狙撃された後のJFケネディが搬送されたことで有名。以降「病院」と呼ぶ)と提携している。「病院で医師のポジションに空きが出た場合は、大学の教職員にそのポジションをオファーする」のが、両者の提携合意事項の一つである。大学の教職員と病院の医師を兼任していた中東出身のナサール氏は、大学の上司にあたるレバイン氏が、宗教的・民族的背景を理由に自分を差別していると感じた。
ナサール氏は、レバイン氏の上司であるフィッツ氏に上記の苦情を寄せ、自分がもし大学の職を辞めても病院で働き続けられるように手配をしてもらった。それからナサール氏はフィッツ氏及び他の同僚に宛てに「レバイン氏のハラスメントが原因で大学を辞める」という手紙を送った。フィッツ氏は、手紙の内容が公衆の面前でレバイン氏に恥をかかせる様な内容であると感じ、その後病院の仕事のオファーに異議を唱えたため、ナサール氏は結局病院の職も失うことになった。
<審理の経過>
ナサール氏は、タイトルセブン違反で大学を起訴した。訴因は、宗教的・民族的背景を理由とするレバイン氏の差別により、大学の職を解雇同然に辞する羽目になった事と、彼がレバイン氏に対する苦情を提出した後、フィッツ氏が報復的行為として彼が病院の職を得る妨害をした事の2点である。地方裁判所の陪審員は両方の訴因を認め、ナサール氏が遡及的給与40万ドルと、3ミリオンドル以上の補償的損害賠償金に値するとした。(同地方裁判所判事は後に、この損害賠償金を30万ドルに減額した。)
この訴訟は、その後、第五巡回控訴裁判所に控訴され、そこでは、「解雇同然」の主張は退けられたが、報復的行為の存在に関しては原判決が維持された。第五巡回控訴裁判所ではプライスウォーターハウス対ホプキンズという1989年の有名な判例を適用し、法で保護されたカテゴリーに対する差別行為や報復的行為は、「直接的因果関係」が証明できなくとも、「動機的要因」のひとつになっていれば十分であるとし、フィッツ氏の行動には少なくとも部分的には、レバイン氏への苦情に関するナサール氏への報復が要因として含まれていると判断した。
<最高裁の判断>
最高裁は、この第五巡回控訴裁判所の決定を覆し、「動機的要因」の基準は報復的行為にまでは拡大されず、タイトルセブン違反となる差別行為のみに適用されるとした。つまり、雇用主の報復的行為を立証するためには、直接的な因果関係を証明しなければならないとした。同判決は、多くの雇用主にとって朗報となったが、この判例を他山の石とする必要がある。
報復的行為を防ぐための重要なポイントは、最初に従業員から苦情があった時点で迅速かつ徹底的な対応をし、事実が確認された時点で改善策を苦情主に報告し、以降再発を防ぐために最善を尽くすことが望ましい。また、その後、その従業員に対して雇用上不利な決定を行なう必要がある場合、十分な根拠があるかを再確認し記録を残す必要がある。また、Eメール等で、苦情を出した従業員をトラブルメーカー呼ばわりすることは、後々「報復的行為」の証拠と看做されかねないので、管理職に対してもくれぐれも注意を促す必要がある。
本記事の内容は、一般的事実を述べているだけであり、特定の状況に対する法的アドバイスではなく、それを意図したものでもない。個々の状況に対しての法的アドバイスは、直接当事務所にご連絡頂くか、専門の弁護士にご相談されることをお勧めする。
J weekly・ https://jweeklyusa.com/